いつ/いかに/どんなテクストを書けるのか。テクストを生み出し続けるにはどうすればいいか。
最近文章を書くということについて色々考えている。
仕事で使う事務的な文章ではなく、人生のアディショナルな領域において、創作であったり、自分の勉強の成果をアウトプットすることであったり、そうした意味でのテクストライティングについてである。
文章を書く技術が非常に不足していると自分では認識している。より正確に言えば、書こうとする気負いだけで実際には書けないということが往々にしてあり、また計画と進捗管理でもって文章を生み出すという行為を自分の制御下に置くということが極端に苦手である。
この文章を書いている今も、衝動的に思いついて、他のやりたいことを全部放り投げて、思考の断片が消えないうちに必死で掬い上げようとしている最中だ。
また、文章を生みたいという衝動と実践との乖離については上述の通りだが、より具体的な文章を書く技術の話も同じである。
これはレポートでも卒論でも修論でもずっとそうだったのだが、なにを書きたいか/書くべきかを具体化できないまま、頭から終わりまで直感とフィーリングで順番に文章を書き続けていき、最後につぎはぎと脱線だらけの奇妙なキメラを生み出してしまうのだ。
文章をいかに構築するか、これは非常に重い問いである。もちろん訓練あるのみというのは分かった上で、ではその訓練をいかに積むのか。
読み易くわかりやすい“ただの文章”ではなく、論理と綿密な思考に裏打ちされた一つのテクストを生み出していくにはどうしたらよいか。
一つにはテクストの断片を大量に生み出し、自分の思考をまず羅列していく、そこから主張の核を取り出し、文章を肉付けし、論理を通し、副次的な情報を付け加えていくのがよいのだとなんとなく思う。ただ、まずこのテクストの断片をどうやって生み出すかという問いも生まれる。
学問の世界から脇道に逸れたままぼーっと生きていると、テクストの生み手でありたいという気負いは徐々に徐々に衰えていき、日常を繰り返し他者の作ったコンテンツを消費するだけの、物言わぬ受け手になってしまう。このことがたまらなく不安なのだ。
いかに/いつ/どんなテクストを構築するか。テクストを生み出し続けるにはどうすればいいか。その糧となるテクストをいかに読み続けるか。
幸いにも、自分は仲間と共に読書会をやることで、ギリギリ学問の世界に接点を保てており、もしかすると今が最後の好機であるということを理解しているつもりである。
読書会という共同体の持つ拘束力、他者という視線、同じ目的を持つ複数の人間が集まって生まれるエネルギーをうまく「書くこと」に向けられるうちになんとか書き続けていきたい。書く習慣を体に染みつかせたい。そういう願望のもとに、今日もとりあえず駄文を生み出し続ける。

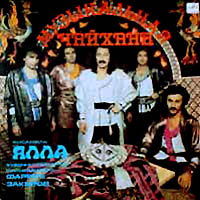
コメント
コメントを投稿