野家啓一2015『科学哲学への招待』 各章要約
しばらく前に、読書猿さんのブログ似合った各章を3行以内で要約するというのをやってみようと思ってやりっぱなしだったのが出てきたので、せっかくだからブログの方にあげてみようと思う。ただ僕はこの辺の知識が全くないため、本当に各章の重要そうな言葉を中心に文章をまとめてみただけの形だけれども。
本は野家啓一『科学哲学への招待』
本書は科学史の概説のようなもので、古代における科学のあり方と、近代において科学の方法論やその定義がどのような過程を経て確立されてきたかを中心的に述べている。その中で起こった論争など、僕にはかなり難しくてちんぷんかんぷんなところも多かったけど、12章の科学のパラダイム論に関する論争や、13章で扱われるソーカル事件などは耳にしたことがある人も多いと思うので、読んでみると面白いのではないだろうか。
各章要約
第一部 科学史
第1章 「科学」という言葉
科学という訳語の意味と、その西洋社会における位置付けの変化を解説。日本では明治期に、世界観や自然観としてよりも個別分野の専門的知識として科学と技術を受容。西洋では両者は古くから独立の概念だった。
第2章 アリストテレス的自然観
古代ギリシアにおける自然哲学の発展により、天文学と運動論(→物理学へ)の理論が形成され、コスモロジーが体系化(地動説、月を境とする宇宙の2つの世界)。しかし、古代ギリシアで確立されたセントラル・ドグマにはそれぞれ欠陥があった。
第3章 科学革命(I)——コスモスの崩壊
12世紀以降、古代ギリシアの宇宙論の受容と発展。キリスト教思想とアリストテレス哲学との融合。のちにコペルニクスが、「一様な円運動」を遵守するため宇宙論の転換を行い、科学革命の端緒に。ついでケプラーが、惑星の完全な円運動が誤謬であることを証明し、従来の天体の幾何学から天体の物理学への道を踏み出した。
第4章 科学革命(II)——自然の数学化
ガリレオによる近代物理学の位置付けは、運動論の刷新にとどまらず質的自然観から量的自然観への根本的な転回を促した。自然を数学的構造を持つものとし、質的な性質を科学的な観測から退けた。論証と実験という方法論もこの時期に確立。ニュートンは天文学と運動論を「万有引力の法則」によって統一し、古代宇宙論に引導を渡した。
第5章 科学革命(III)——機械論的自然観
ガリレオに始まった「有機体論的自然観」から「機械論的自然観」への転回が行われ、デカルトにより「機械論的自然観」が体系化。「物心二元論」による物体・精神の概念が確立し、それによれば、動物も物体であり、精神を持つのは人間のみとされる。しかし、「心身問題」、肉体と精神のつながりをどう説明するかについては現代まで問題として残っている。脳状態と心的状態の「対応関係」の確立にとどまる。
第6章 科学の制度化
17世紀の科学革命は方法論を確立し、「知的制度」としての仕組みを整えた。社会制度としての科学が確立するのは19世紀半ばになってから。12世紀ルネサンスと並行した大学の成立。自由七科に比べ機械技術は低い地位にあったが、17−18世紀にかけて地位が向上。啓蒙主義に端を発する技術教育機関の成立。「科学者」と呼ばれる社会階層が生まれ、科学が制度化、近代化を目指す日本がこれらの制度を輸入。
第二部 科学哲学
第7章 科学の方法
演繹法:普遍的命題→個別的命題
帰納法:個別的命題→普遍的命題
帰納法には有限の事象から無限の事象への適応という飛躍が存在。哲学者たちは帰納法が十分信頼するに足る方法であることを示そうとしてきたが、帰納法の正しさを証明しようとすると循環論法に陥いってしまう。近代化科学は両者の短所を補う「仮説演繹法」を確立し、仮説の発見のための方法も考え出してきた。
第8章 科学の危機
古典物理学は、宇宙の出来事は原因と結果の連鎖により厳密に決定されているという決定論的自然観へ。これは人間の自由意志に関する近代哲学最大のアポリア(解決困難な問題)に。科学においては、古典物理学の世界像の崩壊を意味する。数学の危機と物理学の危機。相対性理論と量子力学の登場により、古典物理学的世界像は完全に崩壊。量子論の考え方では、ミクロの世界は常に確率論的にしか測定できない。
第9章 論理実証主義と統一科学
科学革命の分野で最初に登場した「論理実証主義」は、論理学を概念・名辞を扱うものから命題・文を扱うものへと転換させた。ウィーン学団は、科学的世界把握を宣言し、伝統的哲学に反旗を翻し、ア・プリオリな総合命題を認識から排除。さらに意味の検証可能性テーゼを提唱したが、検証は有限個の事例にしか適用できないため、衰退。また、自然科学から人文科学までを一つの方法によって統一しようとした(還元主義)が、物理学の用語で人文科学を説明するのは困難で、挫折。
第10章 批判的合理主義と決定実験
ポパーによる帰納法の否定と反証の概念の提示は、批判的合理主義を生み出した。ポパーは帰納法の循環論法を避け、科学を観察からではなく探求されるべき問題や疑問から出発すると定義付け、また検証に変わって反証の概念を提示。加えて科学は推測と反駁によって真理へ到達しようとする営みであると主張。直観に反し反証可能性が高い命題こそ科学的な=発展の可能性のある命題とする。
第11章 知識の全体論と決定実験
クワインは、論理実証主義による分析的真理/総合的真理という区分に対し、両者を種類の差でなく程度の差に過ぎないと主張。分析的真理は明確に定義づけることはできず、その証明も結局のところ循環論法に。われわれの知識の体系は全体的なネットワークをなすとして還元主義を否定。知識に対する検証や反証は、知識の体系全体を対象とすべき。
また、複数の体系の間に優劣をつけることは困難で、反証されても体系の中で無害化できる。哲学と科学は知識として連続的であり、両者は協働しうる。プラグマティズムは世界を神でなく行為者の視点から捉える。実験的方法はプラグマティズムの格率に合致。ローティは不変の本質があるとする西洋哲学の立場を否定、哲学を歴史的状況における社会的実践とみなし、、科学を世界を新しい語彙を用いて記述する試みとする。統一性より多元性。
第12章 パラダイム論と通訳不可能性
クーンの問題提起:クーンは、「科学は合理的に進歩する」という通念に疑問符を突きつけた。「パラダイム転換」(=理論は別の新たな理論によって打ち倒される)は論理実証主義的科学観へのトドメ。パラダイム転換の原因や理由には、社会的要因や歴史的条件、心理的要素も加わる。
クーンと彼に反発する科学哲学者との論争。パラダイムという言葉がクーンの定義を離れて一人歩き「考え方の枠組み」という意味で用いられるように。クーンの考える真理:絶対的な最終目標ではなく、理論内部で、パラダイムに相対的にしか使えない。
クーンは非合理主義でも相対主義でもない立場、「多元主義」へ(科学を非人格的なアルゴリズムとしてではなく、歴史的・社会的文脈の中に置かれた科学者共同体の社会的実践として捉え直す)
第三部 科学社会学
第13章 化学社会学の展開
パラダイム論以後、科学社会学のアプローチが不可欠という認識。マートンのエクスターナル・アプローチと科学社会学の誕生。それに続くポスト・クーンの科学社会学「科学知識の社会学SSK」。SSKは、マンハイムの影響を受け、社会的条件が科学者の行動のみならず科学理論のあり方にも影響を与えると考える。またマンハイムと違い自然科学にも「知識の存在非拘束性」を敷衍。SSkに対する科学者陣営の反発は、サイエンス・ウォーズを引き起こした(ex. ソーカル事件)。これを機に両陣営は、専門家支配の傲慢さやラディカルな相対主義を反省。今後は専門家・非専門家が共同で社会における科学のあり方を問うていかなければならない。
第14章 化学の変貌と科学技術革命
19世紀後半の産業革命を経て、20世紀前半の戦間期における科学と技術の融合が世界規模で起こる。国家主導で軍事技術のイノベーションが行われ、そこに科学者・技術者が大量に動員され、短期間に多額の予算を投入、理論的知識を基盤にして技術開発が行われるように。顕著な例:「マンハッタン計画」→戦後の国家によるプロジェクト達成型の共同研究(ブッシュ主義)の基礎を形作った。これは、「科学の制度化」に対し「科学の体制化」と呼べる。
科学は「象牙の塔」から「ビッグサイエンス」へ。この過程で科学と社会との結びつきが強まる「産業化科学」。科学者の歯車化(プロジェクトの管理者⇔被雇用者)。ピアレビューに基づくレフェリー制度を通じた品質の維持・管理システムから、分野横断的かつ知識生産を社会的実践として遂行する研究活動へ→研究に「社会的責任」が求められるように。
第15章 科学技術の倫理
20世紀後半の地球環境問題への警告と、「成長の限界論」による技術楽観主義への懸念。科学技術倫理と社会的責任。現代の科学技術はその複雑なメカニズムがどのような帰結をもたらすかは予測が甚だ困難で、理論的発見と技術的実用化のタイムスパンの短縮→実験室と社会が地続きの状態である。著者はこれを「社会の実験室化」と呼ぶ。
トランス・サイエンスの問題:解決に科学は必要だが、科学のみでは結論を出すことができない問題領域の拡大。倫理的な理由による科学研究の自粛や制裁の強化(クローン・人体実験など)。公共性の問題:科学技術は「絶対安全」ではありえず、リスクをどの程度引き受けるか・どうやって回避するかが焦点に。予防原則と世代間倫理の問題。
専門家と非専門家の知識の落差 ex. 原発事故。専門家への信頼の低下も。現代に生きる我々には市民感覚による「科学技術のシビリアン・コントロール」が求められている。
補章 3・11以後の科学技術と人間
感想
古代から現代までの科学観、特にコスモロジーと科学を中心に扱っている。近代に科学革命が起こり、さらに科学がプロの研究者という社会階層の出現を持って「制度化」される過程を描く。ついで現代における技術と科学の融合と、それに伴い国家と社会の中で「科学の体制化」が行われていることについて論じ、我々は専門家と非専門家の壁を超えて科学技術と向き合っていかなければならないと説く。
議論自体は面白いが、中世を割とバッサリと切り捨てていたのが気になる。もちろん伊藤俊太郎の中世の科学とイスラーム世界からの伝播を読んでいけばいいのだろうが、やはり中世は「科学革命を準備した時代」という一段低い位置に置かれている。
西欧以外の社会における科学への眼差し、社会における位置づけも気になった。個人的にイスラーム世界における近代の科学とのへの態度が特に。この辺は中世のイスラームのいわゆる「進んだ科学」と近代のイスラーム改革運動などで見るべきところがありそうな気が。
なんにせよ、科学哲学、科学と哲学のたどってきた道筋を簡潔に辿れるコンパクトで良い本だったと思う。

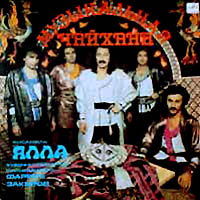
コメント
コメントを投稿